配牌オリ
場と牌効率
麻雀の新戦術トイツ系牌効率について語ってきました。これはトイツ場に軸足を置きながら戦う戦術です。場がトイツ場であれば効果が大きく、通常の牌効率で打っている人と差をつけることができます。
しかし場がシュンツ場や混合場である場合、通常の牌効率で打っている人に対して、トイツ系牌効率は後れを取ることになります。
本来は場に合わせた牌効率で打つのが一番良いです。ですがその場がトイツ場かシュンツ場か、あるいは混合場なのかは、配牌直後にはわかりません。ではどうすればよいのでしょうか。
場がシュンツ場や混合場だった場合、トイツ系牌効率で対応すると、他家と比べて進行が遅れがちになります。とはいえその場合は、貯めている字牌でやり過ごそうというのが、トイツ系牌効率の基本です。これに関しては、これまで語ってきたとおりです。
和了れない手
自分の手と場がかみ合っていないのには、もう一つパターンがあります。それは自分の手牌が悪すぎて和了が見えないことです。麻雀は和了を目的としています。ですから和了が見込めないのは、場と手がかみ合っていないと考えます。
トイツ場かどうかは、配牌時に判断はできません。しかし自分の手が和了れそうかどうかは、ある程度配牌時に判断ができます。
和了が見込めない手の場合、自分が取る戦略には配牌オリがあります。どうせ和了れないのだから、初手から安牌をためておき、いざ他家から攻撃があった時には、それでしっかり降りきるというものです。
配牌オリの手順は、まず中張牌から切り出します。そして字牌・端牌をため込みます。リーチはもちろん、鳴きやドラ切りなど相手からの攻撃の兆候をみて、ため込んでいた安牌でしっかり降り切ります。
配牌オリは他家に振り込む可能性を極限まで減らすことができます。しかし自分の和了は見込めません。つまり完全なる配牌オリを選んだ時点で、その局の期待値はマイナスになります。
配牌オリと国士無双
そこで完全に配牌オリをするのではなく、多少和了の可能性を見るために、配牌オリの中に国士無双の可能性を見ることになります。配牌オリで残す牌と国士無双狙いで残す牌はほぼ同じですから、行為としては同じです。結局は意識の問題で、コインの裏表の関係です。
ただ国士無双の場合、問題になるのはドラが中張牌だった場合の扱いです。もちろん手の中で使うことはできません。かといって切り出して他家に鳴かれるのもよろしくありません。つまりドラを切るか切らないかで、オリか攻めかの決断を迫られているのです。
配牌オリと七対子
そこでドラが中張牌であっても、オリつつも和了の可能性をなくさない方法として、七対子があります。七対子であれば、ドラを手の中で使うことができます。この点で七対子は国士無双よりも汎用性があります。
七対子の待ち牌にしたい山読みしやすい牌は、字牌・端牌ですから、手を進めていくうちに降りやすい手牌になります。
とはいえ、道中でトイツになった中張牌はもちろん手の中に残しますから、手牌が安全牌ばかりになるわけではありません。また、トイツをつくるという性質上、手の中の牌種が少なくなります。なのでオリに関しては、国士無双には及びません。
配牌オリとホンイツ
降りる中で和了を見る方法として、ホンイツ狙いもあります。ホンイツは安全牌となりやすい字牌をため込みやすいです。ドラ色のホンイツにすれば、中張牌のドラも吸収することができます。その点でも隙がありません。
ですが、他家でホンイツ狙いの人がいた場合、字牌が打ちづらくなりますから、その場合、配牌オリの戦略が破綻します。そこまでいかなくても、自分が字牌を絞ると字牌が高い場になりがちです。すると安全牌として持っていたはずの字牌が切れなくなるという、裏目の結果になることもあります。
またドラが字牌の時のホンイツ狙いも、同様の状況が強まりますから、和了とオリ両方とも厳しくなります。
字牌
配牌オリと、それに絡む手役について確認しました。ポイントはドラ牌です。ドラがどの種類かによって、配牌オリと組み合わせる手役を考えることになります。まとめるとこうなります。
ドラが中張牌の場合はホンイツ、あるいは七対子を配牌オリと組み合わせることが望ましい
ドラが字牌・老頭牌の場合は国士無双、あるいは七対子を配牌オリと組み合わせることが望ましい
さてここで、両方に七対子があることに注目です。ドラがどういう種類であるにしても、配牌オリと複合させるのに七対子は有効な役です。ここからどういった戦略が考えられるでしょうか。
ホンイツと七対子
ドラが中張牌で配牌オリする場合、ホンイツに行くのがよいのは前に述べたとおりです。しかしその挙動は相手にばれやすくなります。であれば、ホンイツに偽装した七対子で対抗することができないでしょうか。ホンイツっぽい捨て牌で、待ちは違う色の数牌の七対子という感じです。
実際にやってみるとわかりますが、実現はなかなか難しいです。途中までは捨て牌をホンイツっぽくすることはできます。ですが、どうしても後半にホンイツに見せたい色の牌がたくさん場に出てしまい、偽装が見抜かれやすくなります。
とはいえ、その偽装がたまたまうまくいくこともあります。少しの手間でできるので、ダメもとでやってみるのも一つでしょう。
国士無双と七対子
ドラが字牌・老頭牌の場合、国士無双に行きやすいのは、前に述べたとおりです。そしてそれは当然相手にもばれやすくなります。であれば、国士無双に偽装した七対子で対抗することができないでしょうか。国士無双っぽい捨て牌で、待ちは中張牌の七対子という感じです。
これはそもそも、国士無双が警戒される場になること自体が難しいです。序盤では国士無双の捨て牌が河にみられても、それはほとんど無視されます。少なくとも捨て牌二段目の後半から三段目にならないと、気にしてくれないでしょう。
また、七対子と国士無双の捨て牌は序盤こそ似せることができますが、終盤ではどうしても字牌・老頭牌が切れすぎることになります。特に場に3枚切られた字牌・老頭牌は、七対子として使えませんから手の中に残せません。そしてそれを切った瞬間に国士無双の偽装が暴かれることになります。
とはいえ、国士無双ではないことがばれても、それは七対子っぽい捨て牌であることに間違いはありません。すると中張牌で待つのは出和了期待としてはアリでしょう。
どれだけ和了をみるか
その手牌にどれだけ和了の可能性を見るかによって、狙う手役も変わってきます。
完全に降りるならそれなりの方法をとります。つまりドラは切らず、配牌からは中張牌をどんどん切って、字牌・老頭牌をため込みます。そして相手になにかしら攻撃の兆候が見られたら、それに対応していきます。一切和了の可能性を見ないなら、そういうことも可能です。
国士無双もほぼオリです。ダメでもともとの気持ちで始めて、なにかあればすぐやめて対応するくらいの気持ちでやるべきでしょう。
七対子はどうでしょうか。これはダメなりの足掻きでしょう。無理だとはわかっているけれど、何もやらないよりはマシだという感覚です。頑張れるまでは頑張るけれど、無理ならあきらめることも必要です。
ホンイツは待ちがリャンメン以上になることもあり、和了の可能性も十分追うことができます。またホンイツをされると、他家はその色の牌が切りづらくなります。ホンイツを積極的に仕掛けて、他家の手牌に制限をかけることもできます。相対的に自分の和了の可能性が高めることができます。
まとめるとこうなります。
通常手組 > ホンイツ ≧ 七対子 > 国士無双 > 配牌オリ
左に行けば行くほど和了が見込め、右に行けば行くほど振り込みにくくなります。七対子の扱いとしては、国士無双よりは和了を見ているが、ホンイツほどは和了を見ないというポジションでしょうか。
牌の絞り
自分の配牌が悪く和了が見込めない場合、オリを選択します。オリる中で、ダメでもともとの気持ちで狙う手役が七対子です。
その状況で、自分の下家が役牌を仕掛けたとします。その下家に和了らせたくありませんし、聴牌もさせたくないとしましょう。すると鳴かせないように牌を絞ることになります。
チートイツを狙いつつ、牌を絞ることについて考えてみましょう。
字牌の絞り
役牌からの仕掛けですから、さらに他の役牌を鳴かせたくはありません。また相手の立場になるとオタ風牌も鳴きやすい牌ですから、残されやすいです。そこで字牌全体を絞ることになります。
ただチートイツ含みで進めている自分にとっては、字牌を重視するのはもともとの進行です。なので特に意識することなく進めていても、同様の選択になります。
つまりチートイツ狙うことによって、自然と字牌を絞ることにもなっているのです。
トイツの筋牌の絞り
また、チーをさせて相手の手を進めるのも避けたいです。そのため鳴かれやすい数牌を絞ります。さて鳴かれやすい牌とはどういうものがあるのでしょうか。もちろん相手の捨て牌などによって考えるべきです。しかしそれとは関係なく、自分の手牌だけで意識するべき牌があります。それはトイツの筋牌です。
例えば自分に![]()
![]() とトイツがあるときの
とトイツがあるときの![]() は、単純なペンチャン、カンチャンだけでなく、すでに
は、単純なペンチャン、カンチャンだけでなく、すでに![]()
![]() のトイツがある分、相対的に下家に
のトイツがある分、相対的に下家に![]() –
–![]() の両面受けが残っている可能性か高まっています。つまり鳴かせないために、トイツの筋牌は切らないという選択が生まれるのです。
の両面受けが残っている可能性か高まっています。つまり鳴かせないために、トイツの筋牌は切らないという選択が生まれるのです。
ただトイツ系牌効率においては、筋牌の重要性をこれまでに何度も語っています。それはトイツ場かどうかの見極めをつけるためと説明しました。他家に絞るためではありません。単にチートイツを目指す打ち方と、オリを考えた打ち方では、その打牌の意図は違います。
チートイツで進めているなら、トイツの筋牌を残すのはもともとの進行です。なので特に意識することなく進めていても、数牌の絞りを考えた選択と同様の進行になります。これは字牌の絞りとも類似しています。
つまり、トイツ場を利用して積極的に和了を目指す手筋と、和了をあきらめ半ばオリ気味に進める手筋が同じになるのです。それがチートイツという手役の不思議さであり、面白さでもあります。
親に対するトイツ系牌効率
牌を絞るという話を前章でしました。この牌の絞りは近年その効果が疑われています。というのも、特に「トイツの筋牌の絞り」については、下家の手の進行を遅らせます。すると相対的に対面と上家の和了率が上がります。すると全体としてみた場合、他家の和了率が上がってしまうのではないかという話です。
この話には一理あります。ただそれでも、牌の絞りが有効な場面もあるのではないでしょうか。一つは得点的なライバルが下家の場合です。そしてもう一つが下家が親の場合です。今回はこの下家が親の場合、つまり北家でのトイツ系牌効率について考えてみたいと思います。
麻雀には「親」と「子」という立場があります。その親での和了において、どういうポイントがあるでしょうか。
一つは局が進まないという点です。親に和了られて局が進まないということは、親と点数差をつけられる、あるいは点数差を詰められるうえで、もう一度局がやり直しになるわけです。それは子にとって、ほとんどのケースでうれしくありません。
ならば子は親に和了らせないように、全力で向かうのかというと、単純にそういうわけにはいきません。それがポイントの二つ目、得点が子の1.5倍という点です。得点が子の1.5倍のため親の攻撃に対して、子は対等に戦えません。どうしても、子は引き気味になりがちです。
そこで立場の弱い「子」が協力して「親」に対抗することで、親と対等以上に戦おうとするわけです。ただ子の協力と言ったものの、実際は北家が親に対して絞ることで、その進行を押さえます。その隙に南家・西家が二人掛かりで和了にかけるという形です。少年漫画なら熱い展開ですね。
さて、ここからが本題です。この北家の役割を果たすのに、「トイツ系牌効率」が有効ではないかという話です。これまで述べたように「トイツ系牌効率」は、「3・7牌」を重要視します。すると、自然とペンチャン、カンチャン、リャンメンに必要となる牌を絞ることになります。また前章で述べたように、筋牌を重要視しますので、自然とトイツの筋牌の絞りも行います。
またポンの問題があります。北家がポンをすると、ツモ番を抜かされるのは親以外の人です。すると相対的に親のツモが増えることになり、親の和了率を上げてしまいます。ただトイツ系牌効率は狙う手役がチートイツです。チートイツは鳴いて作れません。つまりポンをしないのです。トイツ系牌効率は、親の和了率を上げないよう、自ら縛りをかけているわけです。
以上を踏まえますと、これまでトイツ系牌効率を使う場面として、「手牌のつながりがバラバラ」「ボロ負け状態」「和了れなくても別にいい」を挙げました。それに「北家」も加えても良いのではないかと思うのです。
むしろトイツ系牌効率は「北家」でこそ、その威力を発揮すると言っても過言ではありません。
では南家はどうでしょうか。親対子の観点から考えると、南家の役割は西家との二馬力で和了を目指すことに加えて、ポンにより親のツモ番を飛ばすことも考えたいです。和了に向かいつつポンをするとなると、チートイツ狙いのトイツ系牌効率ではその役割を果たすことができません。しかし実は南家におけるトイツ系牌効率もあるのです。しかしそれについては、また別の項で述べたいと思います。
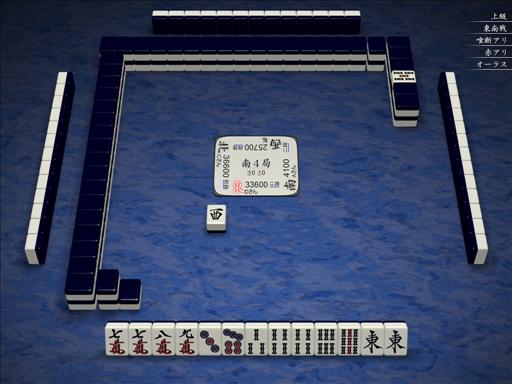
コメント